平成27年9月 年の取材記事一覧
天津地区 NO.01
平成27年9月放送

南部町の北部に位置する天津地区。母塚山や、豊かな田園地区が広がる地域です。



左【赤井さん】
畑で作業をされて休憩中の方を見かけたので話を伺いました。
「畑仕事は面白い」と、とてもいい笑顔で答えてくれました(^^)
そんな赤井さん、なんと大正15年生まれの“90歳!”お元気ですね!
中【畑】
赤井さんが丹精込めて作っていた大豆。イノシシにみんな食べられて、荒らされてしまったそうです。
それでも懲りずに毎年楽しい畑仕事を続けておられるそうです。この畑仕事が元気の秘訣だそうですよ♪
右【背負子】
赤井さん手作りの背負子です。本人曰くは何十年と使っている!とのこと。頑丈に作ったんですねぇ。



左【大塚さん】
この辺りの歴史に詳しい大塚さんを尋ね、この周辺を案内していただきました。
中・右【清水井】
古事記の再生神話の舞台。
この地で兄弟達の策略で、火で焼いた真っ赤な大岩に潰されて命を落とした大国主(おおくにぬし)
その母(刺国若比売-サシクニワカヒメ-)が高天原で天の神に命を乞うたところ、
赤貝の神(キサガヒヒメ)が貝殻で岩から大国主の体をはがし、ハマグリの神(ウムギヒメ)の
母乳とこの清水井の水で練った薬を大国主の体に塗ったところ、大国主は息を吹き返したのだそうです。
そして、一度も枯れることなく沸き続けているそうです。


左・右【清水川神社】
もうひとつの再生神話の場所に案内していただきました。
この神社は大国主命を蘇生した赤貝の神(キサガヒヒメ)とハマグリの神(ウムギヒメ)を祀った神社だそうです。
この二神を、祀っているのはここと、出雲大社内だけなんだそうです。
また、神社の境内には『大国主命蘇生復活の地』の石碑がありました。


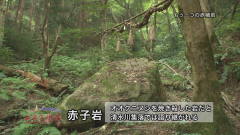
左【看板】
再生神話に関する場所にもう一箇所連れて来ていただきました。道案内の看板には、
『本物と言われている清水川の赤猪岩』とありました。どういうことでしょうか?
中・右【道中/赤子岩】
赤猪岩のある場所まで向かっているところです。木々が鬱蒼としていますね!
清水川集落では昔から、この赤子岩が大国主を焼き殺した岩だと語り継がれているそうです。
この岩には大国主が岩を受け止めた際に出来た頬のくぼみがあると云われています。


左・右【建物/看板】
のどかな田んぼ道を歩いていると、2階建ての建物が。お店でしょうか?
看板が出ていました。「庭の林の森の」お店のようですね。


左・右【店内/前田さん】
店内にはたくさんの植物が置かれていましたよ。前田さんにお話を伺いました。
お店は昨年の5月にオープンしたそうです。この建物は、倉吉にあった蔵を移築して建てたそうです。
今後は、植物の魅力や楽しさを伝えるイベント等を計画されているそうです(^^)



左【野口さん】
前回この地区をそぞろ歩きした時にお世話になった方に会いに来ました。
中・右【大太鼓】
以前も見せていただいた大太鼓をまた見せていただきました。
「やっぱり大きいなぁ!」直径は2m。音を出してみました!ビリビリとした迫力ある音が出ましたよ!


左・右【佐伯さん・胴部分】
この大太鼓を組み立てた佐伯さんです。大太鼓は、革の部分が2枚有っただけで太鼓にはなっていなかった
そうで、佐伯さんが胴の部分を作り現在の太鼓の形に仕上げたんだそうです。
佐伯さんが61歳の時にこの太鼓を作ったということは、現在90歳!お元気ですね(^^)

左【清水谷のふろや】
もう一箇所古事記にまつわる場所があると伺って、行ってみました。
母親神の伊邪那美は、最後に「火の神」を生んで焼死され、出雲国と伯伎国との境の比婆山(ひばやま)に葬りました。
これを「母親山」と呼んだ=この山が現在の「母塚山」であると伝えられています。
母親神の伊邪那美を葬った八百萬(やおよろず)の神々がけがれを祓うみそぎをされたのがここ「ふろや」の泉水であり、この谷を「清水谷」といいます。地域の皆さんで綺麗に保っておられるそうです。
