平成18年2月 年の取材記事一覧
八郷地区 NO.01
平成18年2月
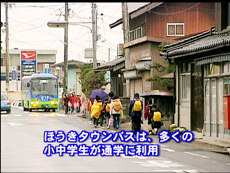


左【ほうきタウンバス】
伯耆町八郷校区は校区がとても広いということで、今回は『ほうきタウンバス』を利用しました。
このバスは、多くの小中学生が通学に利用しています。
中・右【鈴木さん・久古窯】
伯耆町久古で大山焼の窯元をしている、鈴木さんにお会いしました。鈴木さんは、京都で勉強をした後、
昭和47年故郷で窯元をはじめました。大山焼という名前は、明治・大正時代にこの周辺にあった焼き物の名を
頂いてついたそうです。



左【大山焼の作品】
この付近は、中国山地のはずれにあるため、鉄分を多く含んだ粘土が多く、金属色に反射を起こすという特徴があります。鈴木さんは、これについての研究をずっと行っておられます。
中【伯耆町消防団第4分団(八郷分団)】
消防団の方が、消防車の点検をしているところに出会いました。伯耆町消防団第4分団のみなさんは、日々の巡回や一人暮らしのお年寄り宅の雪下ろしをするなど、積極的に活動をしておられます。
右【放水訓練】
僕も、放水訓練を体験させてもらいました。水を放つホースはとても重たかったです。



左【やぎのピオーネ】
次に、ペンション村まで足をのばしてみました。そこで、カルロスランチのご夫妻とやぎのピオーネ(女の子)に出会いました。
ピオーネの大好物は、ビスケット。ご夫妻と一緒に米子の公園に散歩に出かけることもあるそうです!!
中【沖村ペンション】
1976年(昭和51年)、西日本初のペンション村が誕生しました。沖村ペンションはペンション村の誕生と同時にオープン!オープン当初は、3件のみだったペンションは、その後2~3件ずつ増えていったそうです。
昔は、若い女性のお客様がほとんどでしたが、今では、家族旅行で来る人がほとんどで、オープン当初からのリピーターも多くいらっしゃるそうです。
右【手作り味噌】
伯耆町丸山にある丸山交流館では、地元の奥様達が味噌作りをしておられました。
今はまだ白っぽい味噌ですが、熟成が進むにつれて色が濃くなっていくそうです。


左【丸山代官所跡】
冬の間、大山寺の役僧が執務した役所がありました。代官所の近くには、武家屋敷が5~6軒立ち並んでいたそうです。
明治時代には、この場所に芝居小屋があったそうです。
右【常夜橙】
江戸時代のころ、大山に向かう人たちは、この常夜橙の灯りをたよりに歩いたのでしょうね。

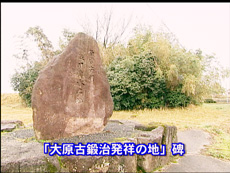
左【後藤さんの家の牛】
梨の剪定中の後藤さんに出会いました。後藤さんのお宅では、和牛を4頭飼育しておられました。後藤さんのひいおじいさんの代から、和牛の飼育を続けておられるそうです。
右【大原古鍛冶発祥の地】
後藤さんに、「刀鍛冶発祥の碑」を案内してもらいました。この地は、平安時代の刀工、『大原安綱』の伝承の地とされています。『太平記』によると、“鬼の手首を切った刀、源氏の宝剣「鬼切」(国宝)は安綱の作と記されています。
