令和6年8月 年の取材記事一覧
金持・板井原地区 NO.02
令和6年8月放送
6年ぶりにおじゃましました。
金持神社の駐車場には県外ナンバーの車が多く止まっていました。



【OI.KAMO】
金持神社の参道にあるお芋屋さん。
お店の方にお話をうかがいました。
約2年半にオープンされたそうです。(2024年8月現在)
梅林さんの前職はガソリンスタンド勤務。
金持神社の入口で生まれ育ったそうです。
20年近く誰も住んでいないご実家でお店を始められました。
金持神社へ参拝される方が年々増えているそうです。
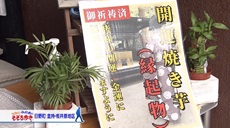
焼き芋械は神主さんによって祈祷済み、焼かれた芋は開運の焼き芋です!
昔のこのあたりには売店はなく、梅林さんご家族が、お札などを販売されていたそうです。
もっと昔は、代々神主さんもされていたそうです。
昔も、バスで参拝に来られる方はいらしたそうですが、
この日も多くの参拝客でにぎわっていました。 毎年約20万人がおとずれるそうです。




冷やしやきいもを食べさせていただきました。
個包装の真空パックに入っています。
中がトロッとしていて甘くておいしいです。夏にはぴったり!スイーツみたいです。
まさに、天然のスイーツですね!

一番甘いと言われている紅はるかを使用。
今後は、干し芋に挑戦してみたいと話してくださいました。
金持神社の参道にお店があるため、参拝客とのコミュニケーションもかなりあるそうです。
毎日、お店の前を通る人数をカウントされているとのことで、
取材にお邪魔したこの日は、10時頃から数え始め、10時40分時点で 114人!
土日だと、各日500人を超える方が来られるそうです。
雨の日の平日でも、平均 100人前後とのこと、
海外の方も増えてきて、英語はできないけど、ジェスチャーでコミュニケーションをとられるそうです。徐々にインバウンドのお客さんも増えてきて、今後さらに賑わいそうですね!


【焼き芋を買われたお客さんへインタビュー】
参拝に来られた方にお話を伺いました。
尼崎から来られたご夫婦。
20回近く来られているとのことで、雪の日や、売店が開いていない時に来られたこともあるそうです。常連さんですね。
広島から家族旅行で。
金持神社については、TikTokで知ったそうです。


【宝篋印塔】
金持神社から1kmほど行ったところにある金持景藤公のお墓。
金持景藤:隠岐の島から脱出した後醍醐天皇が船上山に身を寄せていた時、名和長年公と一緒に護衛を務めました。
そして、京都へ帰る天皇のお供をつとめ、錦の御旗を掲げ終生天皇に尽くしたと言われています。



【板井原集落】
この道は、かつての出雲街道。
難所と言われる、四十曲峠につながっています。
後醍醐天皇も通ったとされ、江戸時代参勤交代の折には、松江の松平家もこの道を通ったと言われています。
板井原宿と呼ばれており、
宿場町だった風情がなんとなく残っていますね。


【基地・パラボラアンテナ】
パラボラアンテナがたくさんあるお宅が・・
ご主人にお話を伺いました。


元気の秘訣は興味を持つこと!基地を見せていただきました。
もともと、子どもの頃から機械が好きとのことで、テレビ・レコーダーがたくさん。
それに合わせるリモコンもかなりの数です。
それぞれのリモコンには番号が書いてありますが、どの機械のリモコンか探すのが大変そうです。
アンプもあるそうですが、時間が長くなりそうなので、今回はここまで、
また次回ですね。




【小さな拠点事業】
片桐さんと自治会長の中田さんにお話を伺いました。
それまでは集落が行ってきた自助・共助の取り組みが、人口減少や高齢化で維持できなくなっている課題があり、従来の自治会より少し拡げた地域を住民が共助で維持していこうという国の施策です。
広島出身の片桐さん、
奥さんのおばあさんが金持に住んでおられた縁で、2024年1月にご夫婦で移住してこられました。
ふるた荘は、2024年5月下旬にオープン。
入口には、建物のオーナーの木彫り作品がずらり。
平日の農作業後や仕事終わりにくつろげるカフェをされています。



月に一度、3集落(金持・後谷・高尾(こお)地区)の住民のみなさんを招待した食事会も開催されています。過去に2回実施。
40名くらい集まり、片桐さんの奥さんが作られたスパイスカレーは好評だったそうですよ。自家製野菜の素揚げが添えられています。

片桐さんは20歳ごろから10年ほどバックパッカーをされていたそうです。
今後は、集落のみなさんと何かをする機会を増やしたい!と話してくださいました。
一緒にお話を伺った中田さんは、『片桐さんが支援員を引き受けてくださってありがたい。地域に希望が見えた。』と話してくださいました。
居心地がいい雰囲気。こういう場所があるのも素敵ですね。
