和田・富益地区 の記事一覧
和田・富益地区 NO.03
令和5年12月 米子市富益地区


【旧 富益小学校 跡】
1963年(昭和38年)に閉校になった富益小学校。
夜見小学校と統合し、現在の弓ヶ浜小学校に。
現在のJA鳥取西部米子弓浜支所があるあたりに校舎があり、石碑の場所に入り口があったそうです。 (2023年12月現在)



当時の写真を見せていただきました。
卒業写真の後ろに映っているのが、校舎です。
永見さんの心の中には、今でも当時の思い出が鮮明に残っているそうです。



【牛頭(ごず)天王神社】
幕末から明治時代の頃に、この地域で疫病が流行っていたそうです。
牛頭天王は、疫病をもたらす神様と言われており、 牛頭天王を信仰することによって、疫病を抑えようとしたそうです。
祠は、平成14年の遷宮時に建て替えられたとのことです。




この地区のとんどさんは珍しく、山車があるそうで、 見せていただきました。


立派な山車には、下に車輪がついていて、地区の住人10人から20人くらいでロープを引っ張って富益神社まで巡行するそうです。
足立さんが子どもの頃にもこの行事はあり、昔は外浜通りを練り歩いて、バスを止めることもあったそうです。山車優先!
子どもからお年寄りまで、住民みんなでロープをひっぱっているそうです。

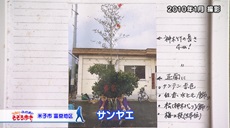
【サンヤエ図】
足立さんが小中学生の頃に実際に作られたこともあるそうですが、 山車が巡行して富益神社へ向かう際、青年団の人が先導して練り歩いていた『サンヤエ』
写真とイラストが残してあります。地域の伝統が受け継がれますね。
コロナ禍で3年ほど中断していましたが、この正月からは久しぶりに実施されるそうです。(2023年12月現在)


【白ねぎ共同選果場】
うかがったこの日は、大山町、日南町、溝口の方からコモに入れて持ってこられたねぎを集めて、皮をむき、長さをそろえる作業をされていました。



根っこと葉っぱを切る機会 → エアーで1本1本手作業で皮をむく → 太さや重さに応じて選別する。
※ベテランになると持っただけで太さや重さがわかるそうですよ!


積んであるのは、農家さんが持ってこられた白ねぎ。
弓浜部にお住いの方は、直接外のかごに。 その他の地域には、それぞれ集荷所があり、そこに集まったねぎをまとめてこちらに運搬して作業されるとのことです。

白ねぎの白い部分ですが、実は葉っぱ。
茎は、根から1cmほどしかないそうです。

土を盛って、日光に当たらないようにすることで白くなる白ねぎ。
砂は簡単に盛ることができますが、強い風が吹くと、ねぎと土の間にすき間ができ、そこに日光があたることで薄い緑色になるそうです。(通称:ボケ)
ボケを防ぐために、風や雨の日の後には砂を盛り直す作業をされているそうです。
12月から1月にかけてが繁忙期。寒い時期に手作業。
こうした苦労を経て、食卓へのぼっています。
出荷はこちらからだそうで、ねぎを冷やしておく設備も見せていただきました。
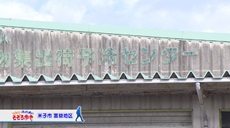


【真空冷却装置】
装置に入れて、真空にしてから冷やす。
真空にして冷やすことで、野菜自体が自分を守ろうとして、糖度にかえるため、甘みが増すそうです。
ひと手間加えることで他と差別化されると話してくださいました。


【富益神社】
約350年前、江戸時代中期に創建
開拓に来られた方たちが、このあたりに立っていた古い木をご神木として神様を祀ったのが神社の始まりと言われているそうです。


宮司は門脇さんのご主人さん。
お話を伺った門脇(理恵子)さんも神職の資格をお持ちで、以前この番組でもお世話になった淀江町大和地区の三輪神社のご出身。
神主さんの会があり、そちらで出会われたそうですよ。

神職の魅力:「社会」という字は、社(やしろ)に会すと書きます。昔から地域のコミュニティは、神社を中心としており、神社に人が集まることで地域社会が形成されていました。 人が集うことで地域が元気になる手助けができれば、と話してくださいました。



現在は、間に県道が通っておりますが、もともとはつながった敷地。
芋代官碑なども見ることができるそうです。


【tocco(トッコ)】
電動キックボードの販売、レンタルをされているお店です。
2023年10月にオープン。 歩行者モードは6km/時速。車道モードは20km/時速 ナンバープレートがあれば公道OK
安全面の指導が必要になるため、現在レンタルの予約は行っていないそうですが、 試乗は随時受付中。
試乗から購入される方が多いとのこと。
免許不要で、16才以上から乗れるそうです。


僕も試乗させてもらいました。
サイクリングロードは歩行者モード(時速6km)。
エンジンをかけて、電源を長押し。
緑色の点滅は歩行者モードです。 アクセルは右手で簡単、ブレーキは自転車と同様に左右に1つずつついています。
最初だけ、助走をつける必要がありますが、あとは自動。
乗ってみて、おもしろかったです!
天気がよい日にサイクリングロードを走ったら、気持ちがいいと思います。
和田・富益地区 NO.02
平成31年3月放送



【弓ヶ浜・白浜青松そだて隊】
多くの地域住民の方がマツの育成に取り組まれていました。
安達さんに話を伺うと、この活動は今年で11年目を迎えたそうです。
この日は松くい虫の予防の為の作業を行っていました。隊のメンバーはおよそ60名ほどで、その約半数が
交代で活動を行っているそうです。この日は400本ほど作業する予定だとか!



【釣船神社】
この地域の歴史に詳しい岸本さんにお話を伺いました。
この神社は山颪源吾が厄除けとして、歓請したそうです。
山颪源吾・・・
米子市和田町出身。江戸時代に江戸・大阪相撲で関脇として活躍した力士。
半日閑話/大田南畝 著
江戸時代後期の随筆。南畝が54年間見聞した雑事を記した書
半日閑話の中に「釣船清次」の話があり、この名前を書いた紙を戸口に貼ると病がたちどころに治った。
この話がたちどころに広まりこの名前を記した札を多くの人が求めたそうです。
このことから、岸本さんは山颪源吾がその札を手に入れて地元に持ち帰ったのでは・・・?とのことでした。
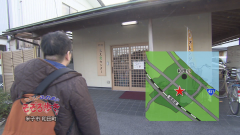

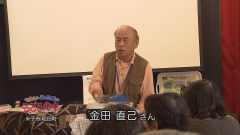
【弓浜支え愛センター/和田ふる里オレンジカフェ】
中に入ってみると、沢山の人がいらっしゃいました。地域の憩いの場として提供されている場所だそうです。
地域の人々で地域活性と、認知症を学び支えあおうという活動をされています。
参加されている皆さんも楽しそうですね!(^^)



【和田公民館】
公民館の中では皆さんが雛人形を飾っていました。
お話を伺った安達さんはこちらに雛人形を寄付されたそうで、昔の雛祭りの様子なども教えていただきました。
飾りを担当されていた先灘さんに伺ってみると、「毎年飾りをしているが、1年に1回しかしないので忘れてしまう(・・;)」
とのことでした。沢山パーツがありますもんね!中には60年以上までの雛飾りもありました。

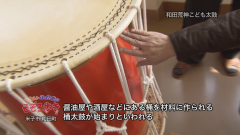

【和田荒神こども太鼓】
公民館の2階では、こどもたちが元気に太鼓を鳴らしていました。
荒神神楽太鼓からの流れを汲む和田の荒神太鼓。
9年前に訪れた際に太鼓を叩いていた小さな女の子も、高校生になっていました!
折角なので一緒に太鼓を演奏させていただきましたよ(^^)
荒神太鼓・・・醤油屋や酒屋などにある桶を材料に作られる桶太鼓が始まりといわれる。

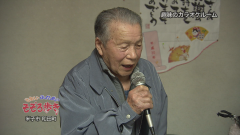

【趣味のカラオケルーム】
和田の方々が集まる場所があるとのことで、伺ってみましたよ!
場所を提供されている矢倉さんに話を聞いてみました。中に入ってみると、立派なカラオケルームが!
「浜愉歩会-はまゆうかい-」という名前で毎週1回集まっているそうです。
最年長の安達さんは、その昔出場した“NHKのど自慢”で特別賞を受賞した実力者!
僕も一緒に歌わせてもらいましたよ(^θ^)~♪
和田・富益地区 NO.01
平成14年5月放送


●おふくろの塩・・・R431沿いを車で走ると気になっていた工場。塩作りの様子を覗かせていただきました。
●釣船神社・・・1865年に造宮された神社。疫病よけの神様が奉ってあります。大正2年に和田神社に移したところ、疫病が発生したため、元の場所に戻したそうです。


●芋代官碑・・・山陰地区にさつまいもの恩恵をもたらした井戸平佐衛門。その遺徳をたたえ、芋代官碑が建てられました。こちらの和田町にある碑は米子市内にある4基のうちの1つで、鳥取県内の芋代官碑で最も古いものです。
●以前、「おにぎり」特集で取材をした味平本店でお昼ごはん!


●モット・・・近所に同じ苗字が多い木村さんに伺いました。モットとは本家のことで、昔は親類が近くに住んで助け合っていこうということから、外浜線沿いに本家があり、分家が日本海の方向へどんどん建っていったそうです。
●富益町の芋代官碑
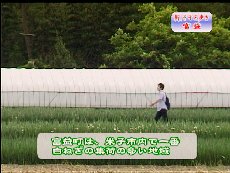

●富益町は米子市内で一番の白葱の生産地としても有名です。
●歴史のあるお宅、長谷川さん邸におじゃましました。祖先の方が鉄砲が好きで「鉄砲屋(てっぽや)」という屋号があるそうです。
